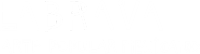メキシコノート 0017
プエブラのタラベラ焼

プエブラ州の州都プエブラは、メキシコシティの東100キロほどのところにある、世界遺産にも登録されているコロニアル都市。1531年にスペインからの植民者たちによってつくられた町で、メキシコ湾岸の港町ベラクルスとメキシコシティを結ぶ中継地として、長い間メキシコシティに次ぐ第二の都市として栄えた。また1862年5月5日、スペインから独立して混乱の続くメキシコの征服をたくらむナポレオン3世が送り込んだフランス軍を、イグナシオ・サラゴサ将軍率いるメキシコ軍が撃退したのがプエブラの街はずれのロレート砦だった。これを記念してシンコ・デ・マヨ(Cinco de Mayo=5月5日)はメキシコで祝日とされている。それだけでなく、メキシコのたいがいの町にはシンコ・デ・マヨと名付けられた通りがあるほど、メキシコにとってこれは特別なできごとだった。
プエブラはまた、おいしい郷土料理でも有名なのだけれど、プエブラと聞いて思い浮かぶのはシンコ・デ・マヨのことよりも料理のことよりも、まず陶器のことである。もともとメキシコには高度なやきものの技術があり、各地でつくられていたのだが、白い錫釉をかけたマジョリカ焼は、スペインの征服によってもたらされた。最初に海をわたってアメリカ大陸にやってきた陶工たちは、まずメキシコシティに落ち着いたといわれている。が、アンダルシア地方出身の陶工たちがプエブラにやってきたのが最初、という説もあるらしい。プエブラといえば陶器、というイメージから考えると、プエブラが最初、というほうがしっくりとくるような気がしてしまうが、どちらが先かはさておき、その作陶法は徐々にサユーラ、アグアス・カリエンテス、グァナファトなどほかの地方にも広がっていった。そして長い年月を経るうちに、スペインから伝わった本来の雰囲気とメキシコらしさが融合し、それに交易で持ち込まれた中国磁器などの意匠の影響が加味されて、なんとも魅力的なメキシコ独特のマジョリカ焼になったのである。残念ながら今もつくられているのは、プエブラとグァナファトだけになってしまったが、どちらの作品からもひと目見るだけでそんな成り立ちが感じられる。プエブラ産もグァナファト産も作陶法としてはマジョリカ焼なのだけれど、20世紀初めくらいからプエブラでつくられるものはタラベラ焼とよばれるようになった。
やきものに適した土や気候、それにロケーションなどのよさに加えて、人口10万人もの先住民都市だった隣町チョルーラにはマジョリカ焼が伝わる以前から陶工たちがいたというよい条件も重なり、プエブラは18世紀まで、ラテンアメリカいちのマジョリカ焼の産地として知られていた。それだけに、一千もの植民地時代の建築が残るプエブラの中心地区の建物には、マジョリカ焼のタイルがあちらにもこちらにもあしらわれている。サンフランシスコ聖堂のファサードや、町の中心にある大聖堂のドーム、現在は博物館として使われている「人形の家」や「砂糖菓子の家」など。極めつけは、プエブラ州立民芸館となった旧サンタ・ローサ修道院の台所。壁もドーム型の天井も総タイル、床にもタイルをあしらったキッチンは、とても贅沢なつくりにもかかわらず、荘厳というよりほのぼのとする印象だ。そんな有名どころのほかにも、ホテルやレストランなどのタイルで飾られた建物がたくさんあるので、近寄ってディテールを観察したり、少し離れて全体のバランスを楽しんだりできるのはプエブラならでは。手づくりのタイルの質感が街全体をあたたかい雰囲気にしている。ところで、そんななかを歩きつづけるとなんとなくプエブラの陶器を手に入れたくなるものである。1824年創業の老舗、ウリアルテは市街地に工房がある。黙々と作業が続く工房で、絵付けされたばかりのお皿やカップが、窓際の陽射しを受けて気持ちよさそうに乾かされている。焼成前のこのパステルな色合いからは想像できない、きりっとした作品が、もうすぐできあがる。