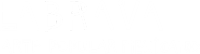メキシコノート 0053
フアン・ルルフォ『ペドロ・パラモ』の町コマラ

コマラにやってきたのは、フアン・ルルフォ『ペドロ・パラモ』の舞台がこの町だからだ。コリマ州都コリマからバスで上ってきた。《父のペドロ・パラモを探しにコマラを訪れたフアン・プレシアドは、フアン・ルルフォの生地であるサユラから下ってきた。》
「Vine a Comala porque me dijeron que aca vivia mi padre, un tal Pedro Paramo.」
スペイン語文学の中で、ガブリエル・ガルシア=マルケスと並び称される重要な作家フアン・ルルフォ。作品の多くに垣間見えるメキシコ革命やクリステロの反乱の雰囲気は、もう遠い過去のことで味わうべくもないが、コマラという実在する地があるなら、そこに行けばじんわりと魔術的リアリズムがしみ入ってくるのではないかと、コマラにやってきたのはそのためなのだ。
ところが、いつか必ず行きたい、との思いが叶って緊張の糸がぷっつりと切れてしまったのか、体調が最悪の状態に。コマラの中央広場のベンチにへたり込みながら、コマラにはこんなふうにぐったりとした人間がよく似合うのだと思ってみる。だって、死者の町だから。《フアン・プレシアドもいつもくたくたではなかったか。映画『ペドロ・パラモ』(1966年版)のフアン・プレシアドも始終のどが乾いていていつも眠そうで疲れていた。》と、くらくらとする頭で考えてはみたものの、晴天のコマラの町は白く美しく明るくあか抜けていた。『ペドロ・パラモ』のなかのコマラは乾いて荒涼としているのに、と拍子抜けした。でも、そんなふうに物語の世界を現実にあてはめようとしたってそうはいかないものだ。無理矢理に印象を物語に引き寄せようとするのは、ただの陳腐な感傷というもの。フアン・ルルフォについての案内板が壁に打ち付けられていた。『ペドロ・パラモ』が26言語に翻訳されたこと、3回映画になったこと、1983年にフアン・ルルフォがスペインのアストゥリアス皇太子賞文学部門を受賞したことという経歴の羅列に混じって、フアン・ルルフォのおじさんフランシスコ・デ・サレス・ビスカイーノが1935年から55年までコマラで司祭を務めていたから、絵のようなこの町をよく訪れ、町と人々を深く愛していた、と。ただコマラへの思いが物語に登場させたのであって、コマラの町の雰囲気を著したのではないのだ。とはいいながらも、なんとなく陳腐な感傷にひたってみたくもあるので、ふらふらの体で町のなかを散策する。ちょっと歩を進めたら川がある。ほら、乾いていない。それでも感傷を求め、橋から上流を眺める。あれ、緑が豊かで瑞々しい。もう感傷はやめにして、美しい瓦屋根と白い壁の町を楽しもう。
コマラ名物、わんこそばのように限りなくタパス(タパ)を出すことで有名な居酒屋が、中央広場に面する回廊に数件軒を連ねている。ミチェラーダを注文し、ライム ジュースと氷が入ったよく冷えた塩付きグラスに、ビールを注ぎ込む、と、次から次へとやってくるタパス。絶好調なら際限なくいける口ながら、きょうはダメである。必死の思いで頬張るが飲み込めない。口のなかはタパスで息苦しい。《フアン・プレシアドは墓のなか。口のなかは土でいっぱいだっただろうに。》
タパスに苦しみながら、物語のなかのコマラを求めるのはもうほんとうにやめたと思ったとたんに、この現実の美しいコマラも『ペドロ・パラモ』のなかにあったことを思い出した。フアン・プレシアドの母ドロレスの思い描く故郷コマラは、「緑の中に白っぽく映え、夜になるとぼうっと輝いて見える」(杉山晃/増田義郎訳『ペドロ・パラモ』岩波文庫)のだ。やっぱり白くて美しいコマラも『ペドロ・パラモ』のコマラなのだった。